ソーシャルメディアを使用する子どもは使用しない子どもに比べて2年後の読解力・記憶力テストの成績が低いことが研究で明らかに

ソーシャルメディアを頻繁に使用する前思春期(10~12歳)の子どもは、ソーシャルメディアをほとんど使わない、あるいは全く使わない同年代の子どもと比べて、思春期初期の読解力および記憶力に関するテストの成績が低いことが、最新の研究により明らかになりました。
Social Media Use Trajectories and Cognitive Performance in Adolescents | Adolescent Medicine | JAMA | JAMA Network
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2839941
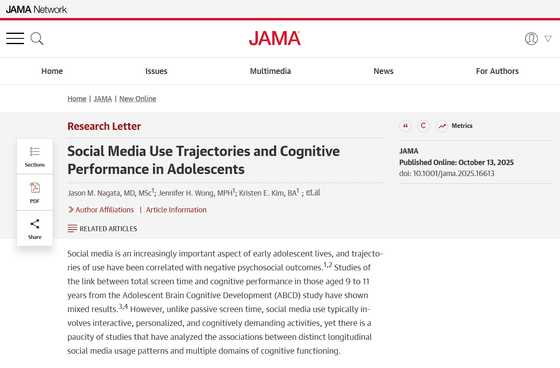
Social media use linked to lower reading, memory scores in preteens : Shots - Health News : NPR
https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/10/13/nx-s1-5571050/social-media-teens-brains-reading-memory
Study: Social Media Might Stunt Students' Intellect | Newsmax.com
https://www.newsmax.com/health/health-news/students-social-media-education/2025/10/14/id/1230253/
Increasing Social Media Use in Preteens May Be Hurting Cognition Too | MedPage Today
https://www.medpagetoday.com/pediatrics/generalpediatrics/117911
現地時間の2025年10月13日、アメリカ医師会が発行する世界で最も権威のある医学雑誌のひとつであるJAMAで、青少年におけるソーシャルメディア利用が認知能力に及ぼす影響を調査した研究論文が公開されました。
これまでの同様の研究の大半は、「ソーシャルメディアの使用が子どもの精神衛生にどのような影響を与えるか?」に焦点を当てるものでした。論文の著者のひとりであるカリフォルニア大学サンフランシスコ校の小児科医であるジェイソン・ナガタ氏は、今回の論文の意義について「特に現在多くの学校が携帯電話の使用禁止を検討している中、授業中のソーシャルメディアの使用が具体的に学習にどう影響するかを理解することは極めて重要です」と語っています。
ソーシャルメディアが子どもたちの認知能力にどのような影響を及ぼすのかを調べるため、ナガタ氏ら研究チームは青少年を対象とした大規模研究のひとつである「ABCD Study」のデータを活用しました。ABCD Studyでは毎年子どものソーシャルメディアの利用状況を調査し、2年ごとに学習と記憶に関するさまざまなテストを実施しています。

ナガタ氏ら研究チームは9~10歳までの6000人以上の子どもを対象にした調査データを活用し、ソーシャルメディアの利用パターンの変化に基づいて、子どもたちを3つのグループに分類しました。ひとつ目のグループは「最初の調査と2年後の追跡調査時の両方でソーシャルメディアをほとんどあるいはまったく利用していない子どもたち(約58%)」で、2つ目のグループは「最初の調査時はソーシャルメディアをほとんど使っていなかったものの、2年後の追跡調査時には1日約1時間をソーシャルメディアに費やすようになっていた子どもたち(約37%)」、3つ目のグループは「追跡調査時に1日3時間以上ソーシャルメディアを利用するようになっていた子どもたち(約6%)」です。
子どもたちは研究開始時と2年後の追跡調査時に認知機能を測るため複数のテストを受けています。例えば、音読認識テストでは、読解力と語彙力が検査され、絵と語彙力のテストでは、聞いた単語と正しい絵を一致させることができるかがテストされます。
調査の結果、「13歳までに1日約1時間ソーシャルメディアを利用していた子どもたち」でさえ、「ほとんどソーシャルメディアを利用していない子どもたち」と比べると、読解力と記憶力に関するテストで、平均1~2ポイント低い成績を収めたそうです。さらに、「1日3時間以上ソーシャルメディアを利用する子どもたち」に至っては、「ほとんどソーシャルメディアを利用していない子どもたち」と比べると、読解力と記憶力に関するテストの成績が最大4~5ポイントも低くなりました。
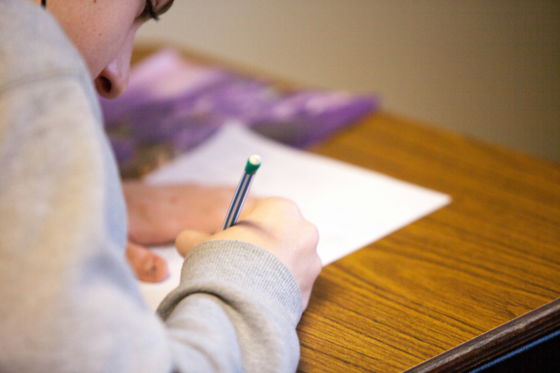
この結果について、論文の付随論説を執筆したカルガリー大学の心理学者であるシェリ・マディガン氏は、「これはまさに、アプリの用量効果を物語っています。多く使用すれば大きな問題になりますが、少量でも問題になるというわけです」と言及。
今回の研究に関わっていないノースカロライナ大学チャペルヒル校の心理学者であるミッチ・プリンスタイン氏は、NPRに対して「これは本当に刺激的な研究です。この研究は、全国の学校から聞こえてくる話の多くを裏付けるものでもあります。つまり、ソーシャルメディアが子どもたちの情報処理能力を変えてしまったせいで、子どもたちは以前と同じように勉強に集中することが難しくなってしまったということです」と語りました。
また、プリンスタイン氏は「子どもたちは変化する対象であるということを理解することが重要です」「短期間で少しでも結果が変わるということは、子どもたちが他の人たちとは違う軌道を描いていることを意味します。つまり、2年後、3年後、5年後には、ソーシャルメディアのヘビーユーザーだった子どもたちとそうでない子どもたちの間には、非常に大きな差が生まれる可能性があるということです」と言及しています。
ナガタ氏は思春期後半になると、子どものソーシャルメディア利用時間が増加する傾向にあることは他の研究で示されていると指摘。13歳以降のソーシャルメディアの利用時間がより多くなったタイミングで、子どもたちの認知能力や学習能力により大きな差が生じている可能性があると指摘しました。

また、ナガタ氏らは大多数の子ども(3分の2)が13歳になる前にソーシャルメディアを利用し始め、平均的なユーザーは3つのソーシャルメディアアカウントを持っていることも突き止めています。加えて、10~14歳の子どもの間でスマートフォン依存症のような症状が高頻度で見られることも明らかになりました。スマートフォンを持っている子どもの半数は、自分がどれくらいスマートフォンを使っているか分からないと回答しており、ソーシャルメディアを利用している子どもの4分の1は、自分の悩みを忘れるためにソーシャルメディアを利用していると回答。さらに、11%はソーシャルメディアの使用が学業に悪影響を与えていると回答しているそうです。
プリンスタイン氏は思春期は脳の発達にとって極めて重要な時期であり、脳が経験に基づいてその構造を微調整する時期でもあると言及。「人生の最初の1年間に次いで、思春期は私たちの生涯で最も大きな成長と脳の最大の再編成が見られる時期です」と語っています。
マディガン氏は今回の論文について、「ソーシャルメディアアプリに年齢制限を設けるなどの、非常に具体的なポリシーを作成する必要があるという十分な証拠を示しています」と語りました。デンマークでは15歳未満のユーザーがソーシャルメディアを利用することを禁止する計画が発表されていますが、この種の施策についてマディガン氏は「少しずつ効果が現れると思います。子どもたちにとって本当に有益なものになるでしょう」と語っています。
・関連記事
ソーシャルメディアやスマートフォンに依存している青少年は自殺行動のリスクが高い - GIGAZINE
子どもをうつ病にしているのはSNSではなく親からの過剰な干渉という研究結果 - GIGAZINE
SNSは子どもや若者にいい影響も与えるが深刻なリスクをもたらす可能性があるとの報告、公衆衛生局長官が政策立案者・テクノロジー企業に行動を促す - GIGAZINE
スマホは子どもにメリットをもたらすとの調査結果、子どもにスマホを持たせる上で注意すべきポイントとは? - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in サイエンス, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article Study reveals that children who use soci….












