まったく同じ内容の講義であっても「教員の性別」によって学生の評価が異なるとの研究結果
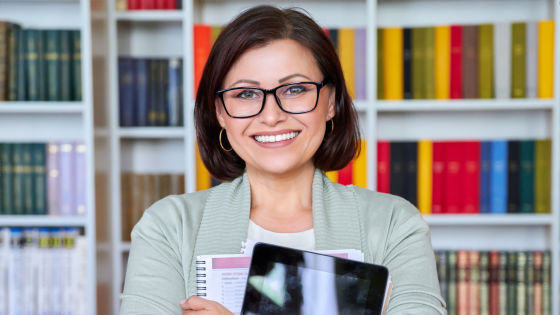
人間は性別に関するさまざまなステレオタイプや偏見を持っており、それが他人の評価に影響していることが知られています。「哲学の教員」の性別が学生による評価に及ぼす影響を調べたイタリアの研究では、たとえまったく同じ内容の講義であっても、教員の性別によって評価が異なってしまうという結果が示されました。
The boys’ club: gender biases in students’ evaluations of their philosophy professors: Philosophical Psychology: Vol 0, No 0 - Get Access
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09515089.2025.2551237
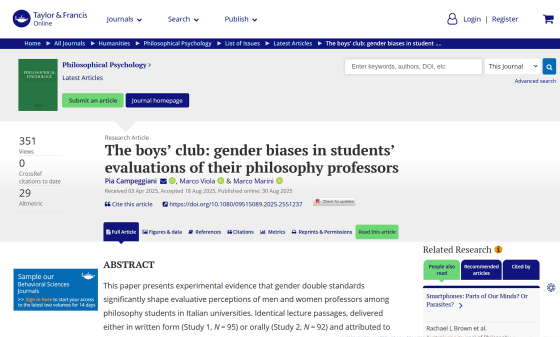
Students rate identical lectures differently based on professor's gender, researchers find
https://www.psypost.org/students-rate-identical-lectures-differently-based-on-professors-gender-researchers-find/
ヨーロッパの学術界全体では、若手研究者のかなりの割合を女性が占めるようになっている一方、教授に占める女性の割合は依然として低いままにとどまっています。中でも哲学は特に男女格差が顕著な分野のひとつであり、イタリアでは哲学科の教授と准教授を合わせた場合、女性の割合はわずか3分の1にも満たないとのこと。
先行研究では、「男性中心」と認識されている分野では積極性・自信・権威といった男性的なものが暗黙のうちに求められ、女性に対して不利に働くことが示唆されています。そこで、イタリアのボローニャ大学で道徳哲学准教授を務めるピア・カンペジャーニ氏らの研究チームは、哲学を取り巻くジェンダーバイアスについて調べるための実験を行いました。実験は2つに分けて行われ、いずれもイタリアの大学で哲学を専攻する大学生と大学院生が被験者として参加しました。
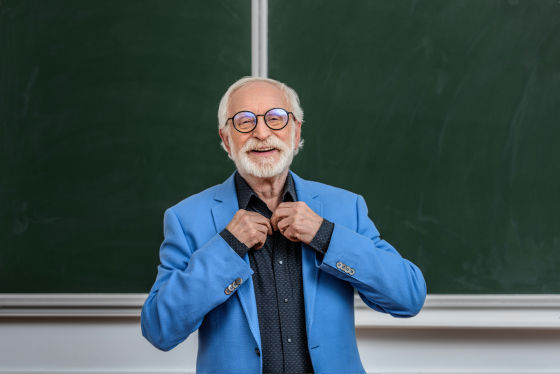
1つ目の実験では、95人の被験者がアリストテレスの倫理学やピエール・ブルデューの象徴権力の概念など、哲学的なテーマに関する4つの講義の抜粋を読みました。各抜粋には作成した講師として架空の男性名または女性名が割り当てられており、被験者らは抜粋の文章を読んだ後に講師の明瞭さや関心、有能さ、自信、配慮、全体的なエンゲージメントなどについて評価しました。
テキストで講義の抜粋を読んだ場合、男性被験者は講師の名前が男性であった場合、一貫して講義をより好意的に評価する傾向がみられ、「その講師によるフルコースの講義を履修する意欲」も高いことが判明。女性講師をより高く評価した唯一の項目は「気遣い」であり、これは女性を保護者としての役割と結びつけるステレオタイプに一致しています。
一方、テキストで講義の抜粋を読んだ女性被験者は「全体的なエンゲージメント」を除いて、ほとんど評価にバイアスを示しませんでした。しかし、「その講師によるフルコースの講義を履修する意欲」は女性講師より男性講師の方が強くなったとのことで、これは女性が公平な評価を意識したとしても残る、根強いバイアスを反映している可能性があります。
カンペジャーニ氏は心理学系メディアのPsyPostに対し、「最初の実験ではテキストを用いましたが、女性被験者の行動に驚かされました。女性被験者は評価において比較的バイアスが少なく、講師が男性か女性かに関わらず、同じように講義を評価していました。しかし、その講師の講義をフルコースで受講するかどうかを尋ねられると、明らかに男性を好む傾向を示しました」と述べています。

2つ目の実験には92人の被験者が参加し、同じ講義の抜粋について話した「典型的な男性と女性の声の特徴を体現する声優」の音声データを聴きました。被験者は1つ目の実験と同様に各項目について評価し、ジェンダーロールに関する信念を測定する追加のアンケートに回答しました。
音声ベースの講義を聴いた場合、男性被験者と女性被験者の両方が「気遣い」の項目を除くすべての側面において、男性講師の方をより高く評価することが示されました。この傾向は、ジェンダーロールについて平等主義的な見解を示した被験者にも当てはまり、暗黙のバイアスが個人の価値観とは独立して作用していることを示唆しています。
カンペジャーニ氏は、「2つ目の実験では音声録音を用いることで、講師の性別をより顕著に際立たせました。その結果、女性被験者は男性被験者と同様のジェンダーバイアスを示したのです」とコメントしました。

カンペジャーニ氏は今回の研究においてさまざまな抵抗に遭遇したそうで、それ自体が教員へのジェンダーバイアスというテーマの繊細さを物語っていると指摘。今後の研究では対象を小中学校にも広げ、ジェンダーバイアスのパターンがどれほど早い段階で発生するのかを検証するほか、哲学以外の分野でも同様の現象が起きているのかどうかを調べたいとのこと。
カンペジャーニ氏は、「私たちの発見のひとつは、明白な平等主義的信念が必ずしもジェンダーバイアスの欠如につながるわけではないということです。言い換えれば、誰もがジェンダーバイアスの影響を受けているのです。私たちは皆、こうした『心のバグ』の餌食になるリスクがあるからこそ、積極的に自己認識と自己批判の精神を育まなければなりません。それと同時に手続き上の安全策、つまり私たちの意思決定や選択、そして評価においてバイアスがより少なく、より公平なものとなるようにするためのルールや構造を整備する必要があります」と述べました。
・関連記事
女性研究者の減少は「性差別」だけではないという主張 - GIGAZINE
社会的な性の概念「ジェンダー」が子どもの中で形成される段階には生物学的な要因も影響していることが浮き彫りに - GIGAZINE
女子の方が男子より「学業の失敗を才能のせいにする」傾向が強い、裕福で平等主義の浸透した国で特に顕著 - GIGAZINE
社会が繁栄して男女平等が高まるほど選択や考え方に男女差が現れることが世界規模調査で明らかに - GIGAZINE
「女性科学者が少ない」と言われるなかで女性研究者が支配的な科学研究の分野がある - GIGAZINE
30年分のデータを調査した結果「男女の脳に有意な差はない」と判明 - GIGAZINE
なぜ男女の間で賃金格差が生じてしまうのか? - GIGAZINE
科学や数学の分野において男女に成績の差があるのか、160万人の高校生のデータから判明したこととは? - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 教育, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Research shows that students' evalua….












