再現に失敗した有名な認知心理学実験まとめ

科学的知見は、誰がいつ行っても同じ結果が得られることで客観性が担保される「再現性」が重要ですが、心理学分野は2010年代初頭から、「再現性の危機」と呼ばれる信頼性のゆらぎに直面しました。従来信じられていた多くの心理的効果は、実験者の実験設定に欠陥があったり解釈にバイアスが含まれていたりすることで再現性に欠け、実際には存在しないか効果が弱いと判明しています。再現性の危機により信頼性を失った心理学実験について、科学や哲学に関するトピックを扱うブログを運営するマルコ・ジャンコッティ氏が有名なものをまとめています。
Famous Cognitive Psychology Experiments that Failed to Replicate - Aether Mug
https://aethermug.com/posts/famous-cognitive-psychology-experiments-that-failed-to-replicate
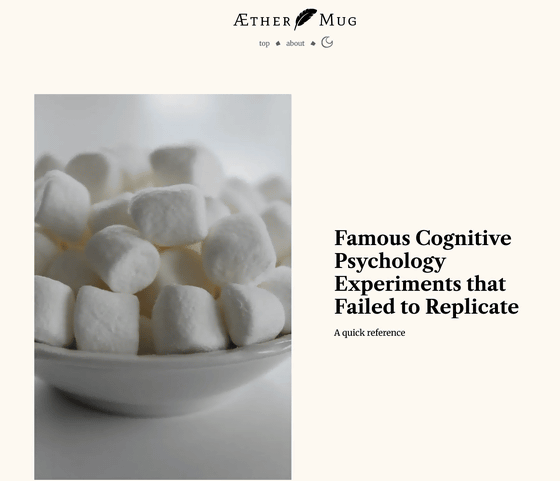
「再現性の危機」は心理学や社会科学、生命科学などの分野で2010年代初頭から注目された問題で、「過去に発表された研究の多くが、他の研究者が追試をした場合に同じ結果を得られない」という学問全体の信頼性が疑問視されている状態を指します。2015年に心理学研究者のグループが直近の心理学研究論文100本の再現を試みたところ実験結果を再現できたのは39本しかなく、総合学術雑誌のNatureが実施した調査では、自分以外の科学者が発表した実験を再現するのに失敗したことがある研究者の割合は70%以上で、全体の50%以上は自分自身が行った実験を再現するのに失敗していることが判明しました。
科学の「再現性」が危機に瀕している - GIGAZINE

by Carlos Henrique
ジャンコッティ氏は「再現性の危機が注目されたのは10年ほど前の古いニュースで、当時から再現性が疑われた不名誉な研究結果は漠然と認識されるのみでした。しかし、認知心理学分野のほとんどの研究結果は実際に再現性があるにもかかわらず、一部の研究のせいで分野全体への信頼が損なわれているのは残念であるため、どれが真実でどれが真実でないのかははっきり認識する必要があります」と語り、再現性が疑われた研究のうち有名なものをリストアップして解説しています。
・自我消耗効果
「私たちがセルフコントロールする自我や意思力には『バッテリー』があり、日々自制心を働かせるにつれて徐々に消耗していく」というのが自我消耗の考え方です。自我消耗に基づくと、セルフコントロールを要するタスクが重なると、その後のまったく別のタスクにおいて、セルフコントロールが消耗して阻害される可能性があります。1998年にアメリカ人社会心理学者のロイ・バウマイスター氏らが自我消耗効果を実証した論文を発表したのが代表的ですが、2016年に実施された追試研究では、「実験効果は疑わしい」と結論付けられました。
さらに、自我消耗効果と結び付けられた「ブドウ糖を摂取すると消耗した自制心がチャージされる」という論文についても、後に再現性が確認できず、元の仮説には否定的な見解が強まりました。
・パワーポージング効果
腰に手を当てて立ったり、腕を上げたりといった体を伸ばす姿勢を2分ほどとると、テストステロンが増加し、ストレスホルモンのコルチゾールが減少し、自信とやる気が満ちてくるというのが「パワーポージング効果」です。2010年にエイミー・カディ氏らの論文で実証されましたが、2015年に複数の研究者がその効果は実験で再現できないと報告しました。結果として、2010年の論文の共著者であるダナ・カーニー氏は2016年に、「パワーポージング効果に関する見解を改めます。オリジナルの実験に関するいくつかの事実はサンプルが小さく信頼性が低く、本物だとは信じられません」という声明を発表しました。

・プライミング効果
「プライミング効果」とは、先行刺激によって行動に影響が出る現象を指します。「コックリさん」のようなオカルト現象も、プライミング効果が影響していると心理学的には考えられることがあります。プライミング効果を実証した1996年の論文では、高齢者のステレオタイプに関する語句やイメージを先行刺激として与えられた直後の参加者がゆっくり歩いたり、無礼さに関する概念を与えられた参加者は他の人の発言をより遮るようになったりといった結果が示されました。この論文は2012年の追試で有効性が疑われ、「無意識のプライミングは実際に存在するが、1996年の論文で示されたものは信頼性が低く、違うメカニズムが関与している」と結論付けています。
西洋版コックリさん「ウィジャボード」の科学的説明を心理学教授が考察 - GIGAZINE

・ESP予知効果
「超感覚的知覚(ESP)」はテレパシーや予知、透視などが含まれる知覚能力で、超能力の一種とされます。2011年の論文では、1000人以上の参加者が後に発生するに刺激イベントを予知または予感として感じられるかをテストしました。論文では「場合によっては、既存の推論プロセスでは予測できない将来の出来事を予測できることがある」と結論付けられましたが、後の追試では科学的に支持されない結論だと判断されています。
・清潔さと道徳心の効果
2008年にイングランドのプリマス大学の研究者らが発表した論文では、清潔な状態を保ったり、清潔さについて考えたりすると、人々はより道徳的な判断が甘くなるということが実験で示されました。2014年に再現実験が行われた結果、元の効果量を検出するためのサンプルサイズを用いても清潔さと道徳的判断を結びつける証拠は得られず、「元の実験はサンプルサイズが小さく偏った結果になった」と考えられています。
・飢餓とリスク
欲望の対象への接近を示す本能的な手がかりが与えられた場合、人々は消費行動に伴うリスクよりも、即時の満足感という期待される報酬に過度に影響される原因となる可能性があります。2006年の論文では、時間をかけてチョコチップクッキーを獲得するゲームに参加した人々のうち、クッキーを実際に見て焼きたての匂いを嗅ぐことができた参加者は、「負けるかもしれない」というリスクを負ってまで報酬を手に入れようとするという結果が示されました。この実験は2016年の再現実験で主要な効果は観察できず、「広く信じられている仮説を再考する必要がある」と結論付けられています。

・心理的距離と解釈レベル理論
「あるタスクの期限が明日の場合は、その難しさについて心配するが、同じタスクをずっと先の未来に計画すると、そのタスクの魅力に気づく」という、「心理的に遠い」出来事はより抽象的に処理され、「心理的に近い」出来事はより具体的に処理されるという考えがあります。1998年と2010年の論文が代表的ですが、この理論の妥当性については多くの疑問が呈されており、スウェーデンのヨーテボリ大学心理学部の研究者らが主導して、世界中の73の研究所が協力してこの理論を検証しています。
・排卵と好みの影響
女性は、生理周期の中で比較的妊娠しやすい日には、妊娠しにくい日と比較して、イケメンに性的魅力を感じやすいということが2014年のメタ分析で示されました。この論文の理論は再現できないことが複数の論文で指摘されており、排卵が好みに与える効果については指示できないという研究が優勢です。
・マシュマロテスト
マシュマロテストとは、スタンフォード大学の心理学者によって1960年代後半から1970年代前半にかけて行われた有名な研究で、子どもに対し「すぐに得られる少ない報酬か、我慢した後にもらえるより大きな報酬か」を選択させた場合、報酬のマシュマロを我慢できたグループの方が後の人生でより優秀だと評価されたというもの。「子どもの頃に自制心を持っている人は、将来的に社会的成功を収める可能性が高くなる」ことが示された実験です。
しかし、2018年に発表された研究では、マシュマロテストの結果は「限定的」であり、幼い子どもが1個目のマシュマロを我慢できるかどうかは、子どもの自制心ではなく、大部分が「子どもの社会的・経済的背景」に左右されるということが示されました。要するに、学歴が高く裕福な親を持つ子どもは普段から十分なリソースを与えられているため、目の前のマシュマロを食べずに我慢できますが、その子どもが将来的に成功したとしてもそれはマシュマロを我慢する自制心に基づくものではなく、「学歴が高く裕福な両親を持つ」という環境の影響が大きいと結論付けられました。
子どもの自制心が将来を左右するという「マシュマロ実験」が再現に失敗、自制心よりも大きな影響を与えるのは「経済的・社会的環境」 - GIGAZINE

by Blaque X
・女性の数学成績
「女性は男性に比べて数学の能力が劣っている」という固定観念があります。このステレオタイプな考え方が不安や脅威となって実際の成績に影響を与えると考えた論文では、テストに性差は影響しないと説明した上で数学の難しいテストを実施したところ、男女の成績の差をなくすことができたと実証されました。この実験は多くの追試やメタ分析で再現せず、効果はあるかもしれないが非常に小さいもので、「普遍性や強度が過大評価されていた可能性が高い」と考えられています。
・笑顔を作ると気分が良くなる
「表情は感情を表すだけではなく、感情体験に影響を与える」という考えがあります。1998年の論文では、マンガを読む際にペンを歯に挟む(笑顔のような表情を強制する)場合と、唇でペンを挟む(笑顔を作らない)場合で比較したところ、笑顔を作った状態の方がマンガをより面白いと評価したことが示されました。しかし複数のメタ分析の結果、表情が感情にフィードバックする可能性は認めつつも、実験の効果の強さには疑問が呈されました。
・モーツァルト効果
「幼い頃からクラシックを聴かせると子どもの知能に良い影響が出る」という考えのことを「モーツァルト効果」と呼びます。1993年にNatureの論文で実証され、アメリカ人の8割が信じているとされていましたが、その後のさまざまな論文で再現が驚くほど困難であることが判明しています。
モーツァルトを聴かせても子どもの知能は上がらないことが研究で判明 - GIGAZINE

By sean dreilinger
・バイリンガルは賢い
バイリンガルであることは、注意力、タスクの切り替え、実行制御において大きな認知的利点をもたらすという考えがあり、2012年の論文ではバイリンガルが成人期の認知機能に及ぼす影響が検証されました。論文では、バイリンガルは成人期にはやや影響が弱いものの、高齢期には認知機能の低下を防ぐという「認知的予備力」に大きな役割を果たすと示されましたが、2018年の追試では限定的で特定の条件に依存した効果のみが認められ、普遍的なメリットを示すには証拠が弱いと判断されています。
再現性の危機に直面した多くの実験は、効果が偽りや全くのゼロということはほとんどありませんが、元の論文で示されたほど強くはなく、大きく誇張されていると考えられているものが多くなっています。ただし、追試の質にもばらつきがあり、再現されないのは元の実験に問題あるのか、条件が異なっているため再現できないのか判別が難しいこともあります。ジャンコッティ氏が挙げたリストは代表的なものであり網羅的ではないため、「有名な研究で、誤りだと証明されたものを見逃していたら、ニュースレターから返信してください」とジャンコッティ氏は呼びかけています。
・関連記事
「運動が認知機能に及ぼす影響についての研究には多くのバイアスが含まれている」との報告 - GIGAZINE
「現代っ子は我慢ができない」は間違いだとマシュマロテストで判明 - GIGAZINE
子どもの自制心が将来を左右するという「マシュマロ実験」が再現に失敗、自制心よりも大きな影響を与えるのは「経済的・社会的環境」 - GIGAZINE
科学者たちの生の声から分かった「科学が直面している大きな7つの問題」とは? - GIGAZINE
科学の「再現性」が危機に瀕している - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in サイエンス, Posted by log1e_dh
You can read the machine translated English article Famous cognitive psychology experiments ….












